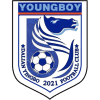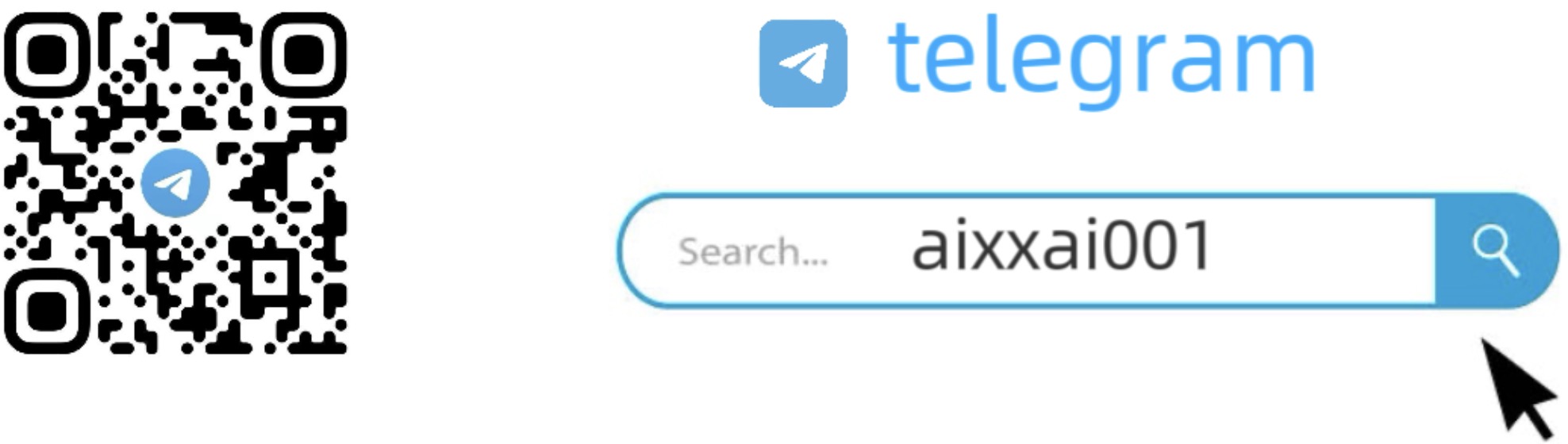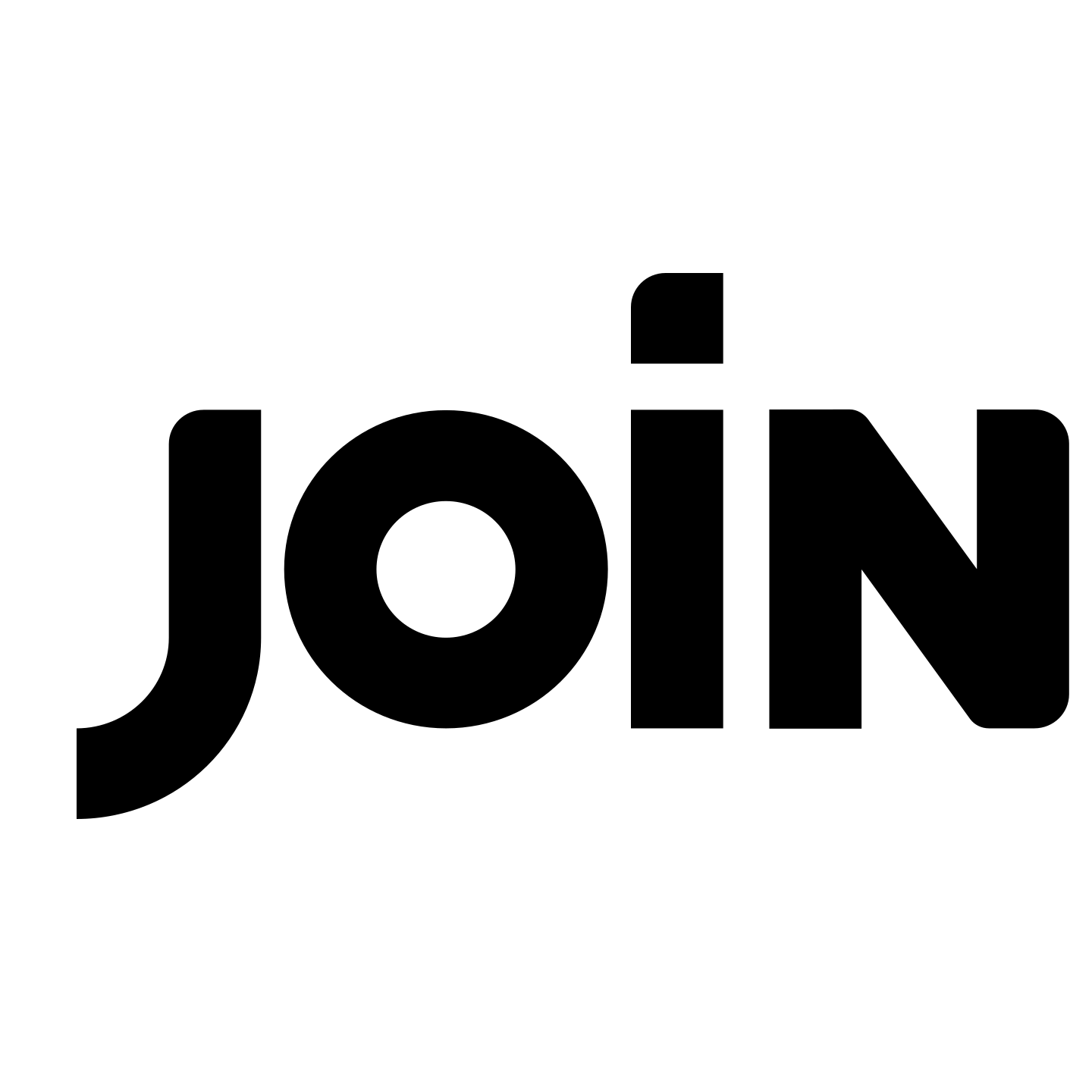【大相撲】審判の舞台裏:秀ノ山親方が語る勝負判定の秘話と危険な瞬間
秀ノ山親方が大相撲の審判の役割とその舞台裏を語る。勝負判定のプロセスや危険な瞬間、審判の苦労とやりがいを紹介。

審判の役割と舞台裏
大相撲では、力士同士が土俵上で白熱した攻防を繰り広げる一方で、競技の進行と勝負判定の役割を担っているのが審判の親方衆です。土俵だまりに鎮座する審判は、どのような視点で取組を見つめているのか。その知られざる苦労とは…。元大関琴奨菊の秀ノ山親方(41=本紙評論家)による連載「がぶりトーク」では、審判の仕事の舞台裏を紹介します。
審判の配置と役割
本場所の取組の場合、土俵だまりに座る審判は通常5人。正面に審判長がいて、東西に1人ずつ。向正面の行司だまりには2人が並び、東寄りの審判は時計係も務めます。審判の親方は土俵下から漫然と相撲を眺めているわけではありません。
勝負判定のプロセス
全体の勝負の流れから、力士の足が俵から出てないか、体は残っているか。攻防の中で、まげに指が入っていないかも見ています。どちらかの力士が一方的に攻めていても、途中で足の甲が返っていれば負けになります。力士が土俵から落ちてきても、よけながら目を離さずに勝負を見極めます。完全に勝負がつくまでは、一瞬たりとも気を抜くことはできません。
物言いとビデオ判定
きわどい勝負や反則の可能性があれば、物言いをつけて審判で協議をします。必要に応じて、審判長が無線でビデオ室に連絡して確認をします。ビデオ係の審判は1人、関取の取組からは2人がつきます。NHKの中継とは異なる四方の角度から、モニターのスロー映像で繰り返しチェックします。ただ、最終的に勝負を判断するのは、現場にいる審判になります。
審判長の役割
審判長は関取の取組では部長や副部長が務めますが、幕下以下はそれ以外の親方が担当します。物言いがついた際、協議の結果を説明することも大事な役目です。まずは行司軍配がどちらに上がったか。基本的なことですが、ここを言い間違えると、お客さんや力士が混乱してしまうので気を付けます。あとは勝負の流れを踏まえながら、協議のポイントを簡潔に説明します。私も慣れるまでには時間がかかりました。
審判の危険と苦労
審判の仕事は危険とも隣り合わせです。土俵から落ちてきた力士とぶつかって、大ケガをすることもあります。私はケガの経験はないけれど、足の上に乗られることは普通にある(苦笑い)。力士に踏まれて、はかまが破れてしまうことも珍しくありません。その場合は支度部屋に戻ってから呼出さんに応急処置で仮縫いをしてもらい、場所後に直します。
審判のやりがい
審判は体力と集中力が必要な仕事ですが、力士たちの熱戦を一番前で見届けるのは、とてもやりがいがあります。私の先代師匠(元横綱琴桜)も、審判の時は体が動いてしまうほど力が入っていた(笑い)。今はその気持ちが分かります。ファンの方々も取組の合間、審判にも目を向けていただけたら、大相撲の楽しみ方が広がるかもしれませんね。