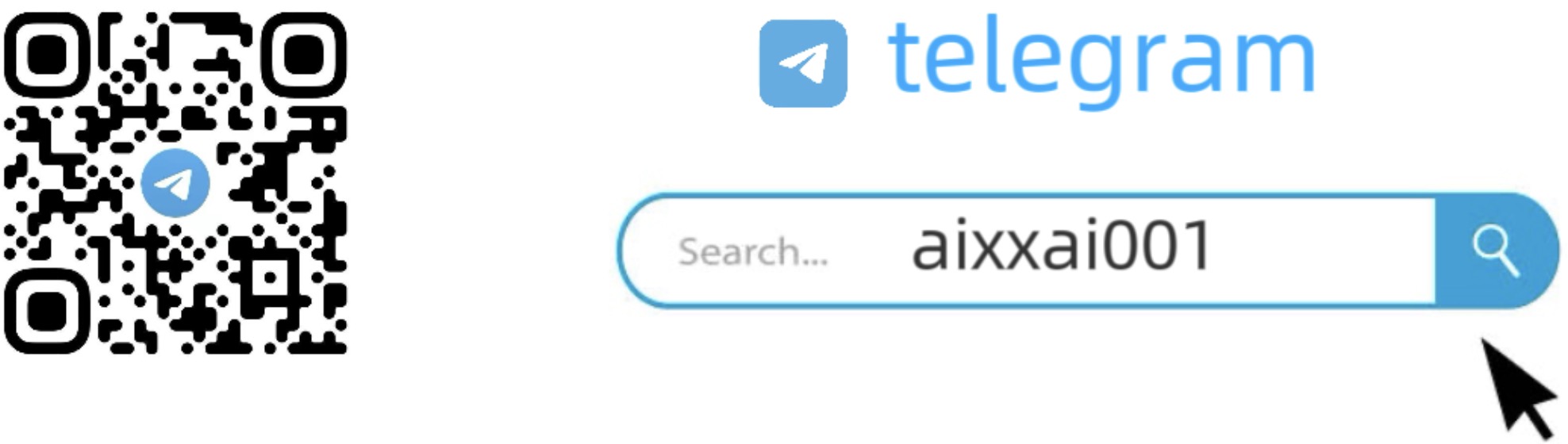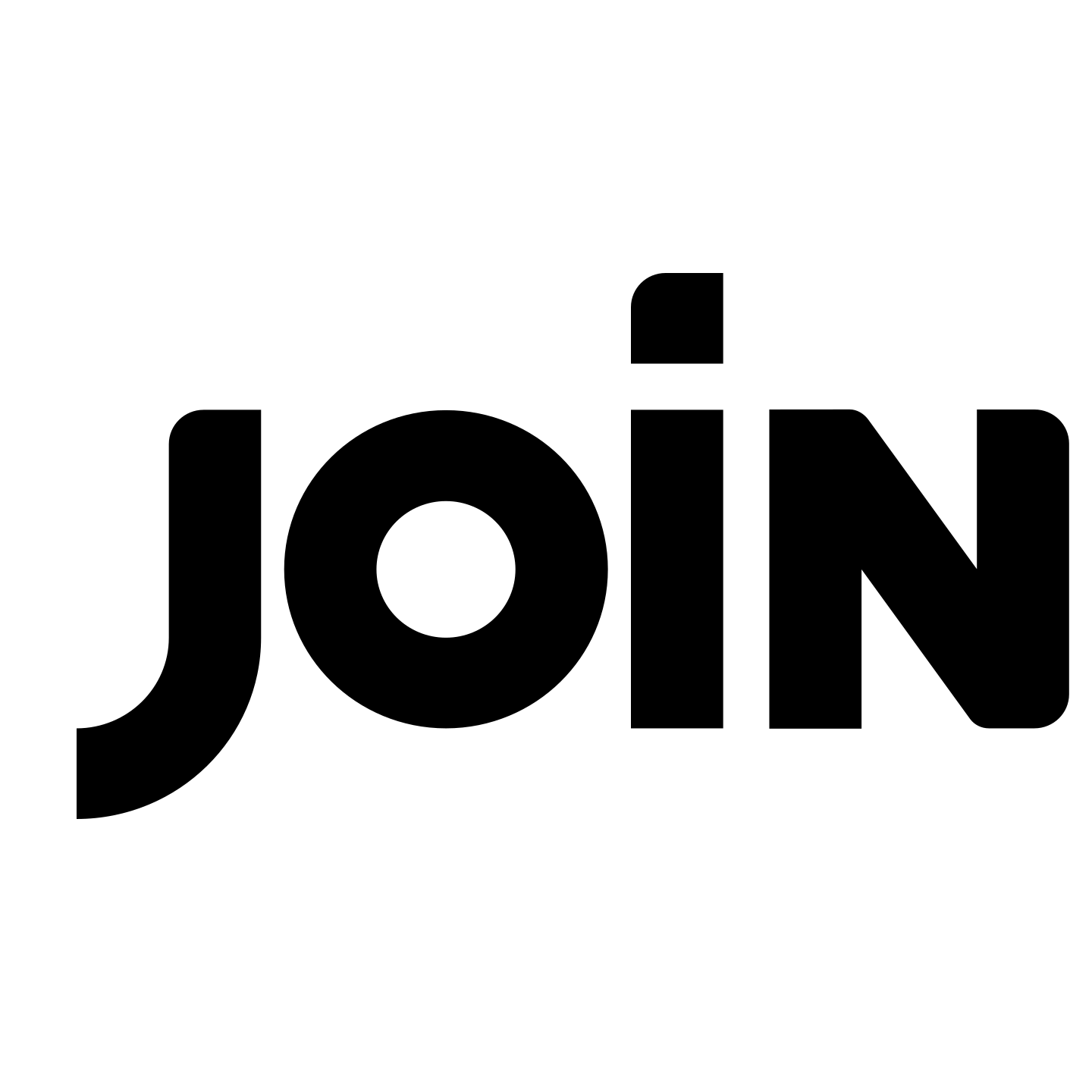大相撲の幻の決まり手:70年間未出現の4技の秘密
大相撲の決まり手の中で、70年間一度も出現していない4つの幻の技について詳しく解説。その難易度と未出現の理由を探る。

大相撲の決まり手とは
大相撲において、勝敗が決した時の技を「決まり手」と呼びます。日本相撲協会が現在定めている82手の中には、幕内ではまだ一度も出ていない決まり手が存在します。その中でも特に「掛け反り」、「たすき反り」、「撞木反り」、「外たすき反り」の4つは、70年間一度も出現していない幻の技として知られています。
幻の4技の詳細
掛け反り(かけぞり)
相手の差し手の脇の下に自らの頭を入れ、踏み込んだ足で切り返し相手を後ろに倒すか、外掛けで反り倒す技です。
たすき反り(たすきぞり)
相手の差し手の肘を抱えながら潜り込みつつ、もう一方の手で相手の足を内側から取り体を反らせて後ろに倒す技です。
撞木反り(しゅもくぞり)
たすき反りと同じ形で懐に入った後、相手を肩にかつぎ上げてから後ろに反り倒す技です。
外たすき反り(そとたすきぞり)
相手の差し手を抱えながら、もう一方の手を相手の差し手側の内股に入れ、体を反らせて後ろに倒す技です。
4技が未出現の理由
これらの技は、相手の懐に潜り込んだ上で体を反らせるという共通点があります。しかし、相撲では一般的に、相手と適度な間合いを取り、低い体勢から攻めることが良しとされています。これらの技は相手に密着することで動きが制限される上、一度とられると一気に戦況が悪くなる背中をさらすことにもなります。
さらに、技の体勢に入れたとしても、相手に上から体重をかけられ潰される、担ぎ上げた相手に暴れられ体勢を崩すといったリスクがあります。また、力士の大型化が進んでおり、相手を反り倒したり担ぎ上げたりすること自体が困難になっていることも大きな要因です。
まとめ
大相撲の決まり手の中でも、特に難易度が高く、70年間一度も出現していない4つの幻の技について詳しく解説しました。これらの技が未出現の理由は、技の特性や現代の相撲の流れによるものと考えられます。今後、これらの技が出現する日が来るのか、注目が集まります。