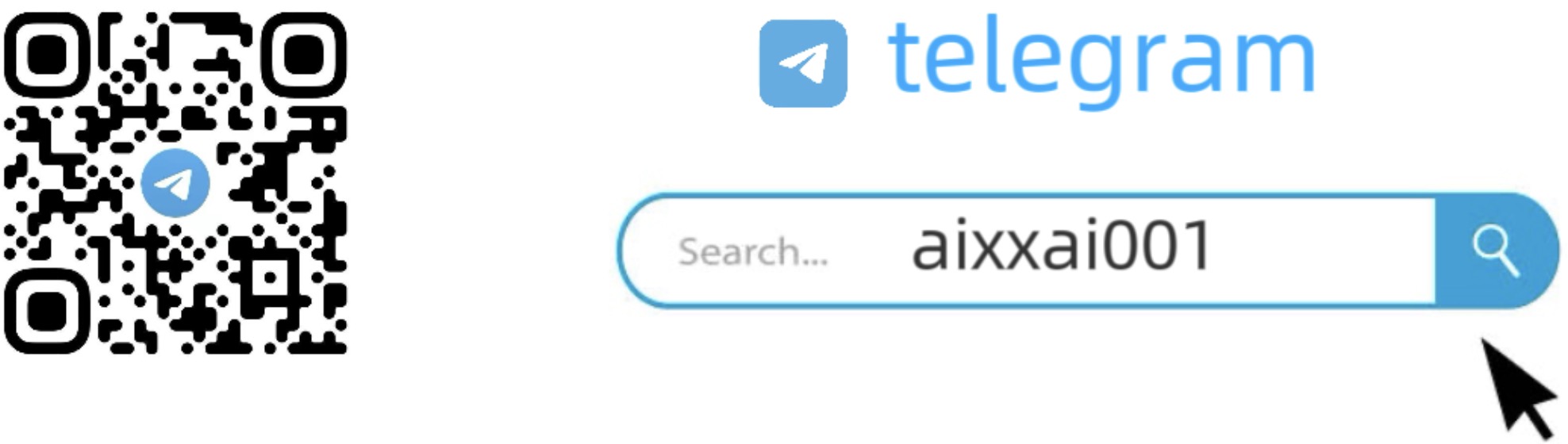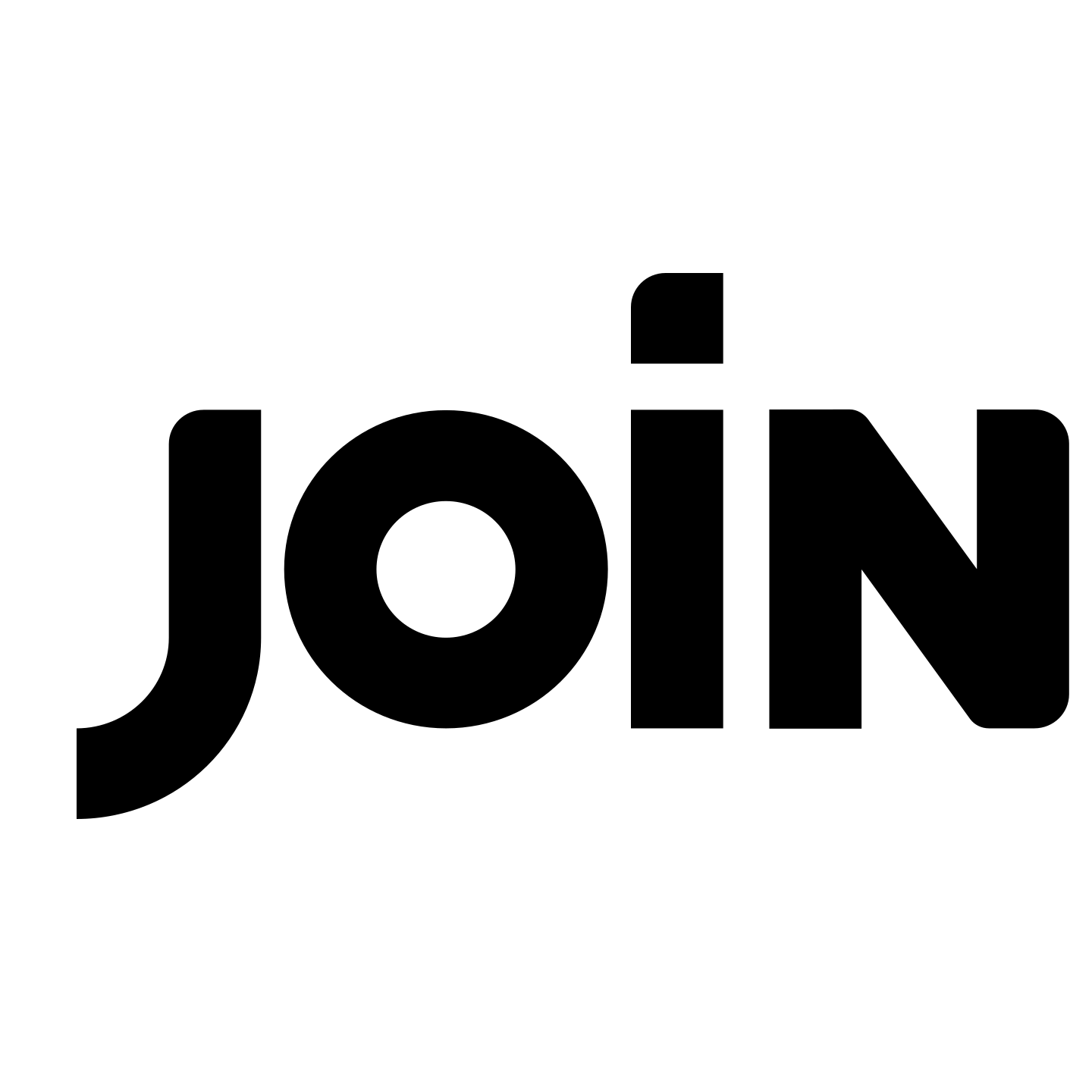大学野球の聖地から紐解く 日本野球場の歴史と進化
明治時代の草創期から現代まで、大学野球を軸に日本の野球場発展史を詳細解説。甲子園誕生秘話から戦前のプロ球場事情まで、貴重な歴史資料を交えて紹介。


大学野球黎明期の球場事情
1878年に新橋アスレチック倶楽部が建設した「保健場」を皮切りに、早稲田戸塚球場(1902年)や慶應三田綱町球場(1903年)など、私立大学が相次いで専用球場を整備。
全国大会を支えた関西の球場群
- 1915年 豊中グラウンド(第1回全国中等学校優勝野球大会開催)
- 1917年 鳴尾球場(阪神電鉄初代本拠地)
- 1924年 甲子園球場完成(収容人数5万人の当時東洋一)
東京の大学野球聖地誕生
1926年完成の明治神宮野球場は:
- 東京六大学野球連盟の主要開催地
- 天然芝とバックスクリーン付きの先進設計
- 学生野球の殿堂として現在も現役使用
プロ野球台頭と戦禍
| 1930年代のプロ球場建設ラッシュ: | 球場名 | 完成年 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 後楽園 | 1937 | 日本初の多目的スタジアム | |
| 西宮 | 1937 | 阪急電鉄がプロ参入用に建設 | |
| 上井草 | 1936 | 東京初のナイター設備 |
戦時中の悲劇:太平洋戦争で主要球場の70%が焼失。甲子園は陸軍施設に転用されるなど、野球文化存続の危機を経験。
現代への継承
現存する戦前建築の明治神宮野球場では、2023年最新の:
- 地下耐震構造
- LED照明システム
- バリアフリー改修 を実施し、伝統と革新の融合を実現。