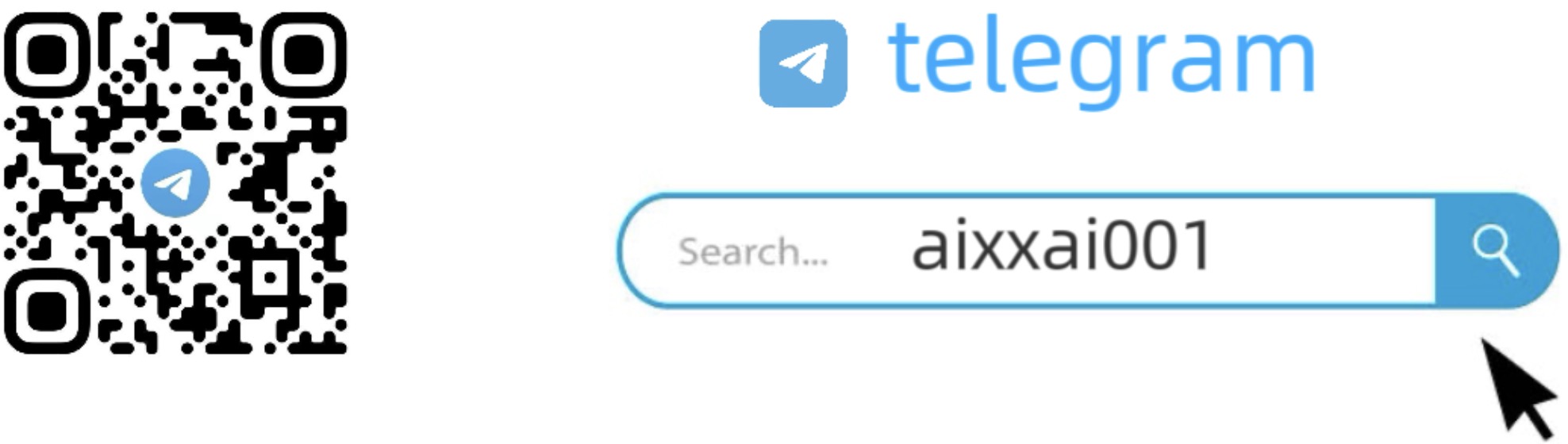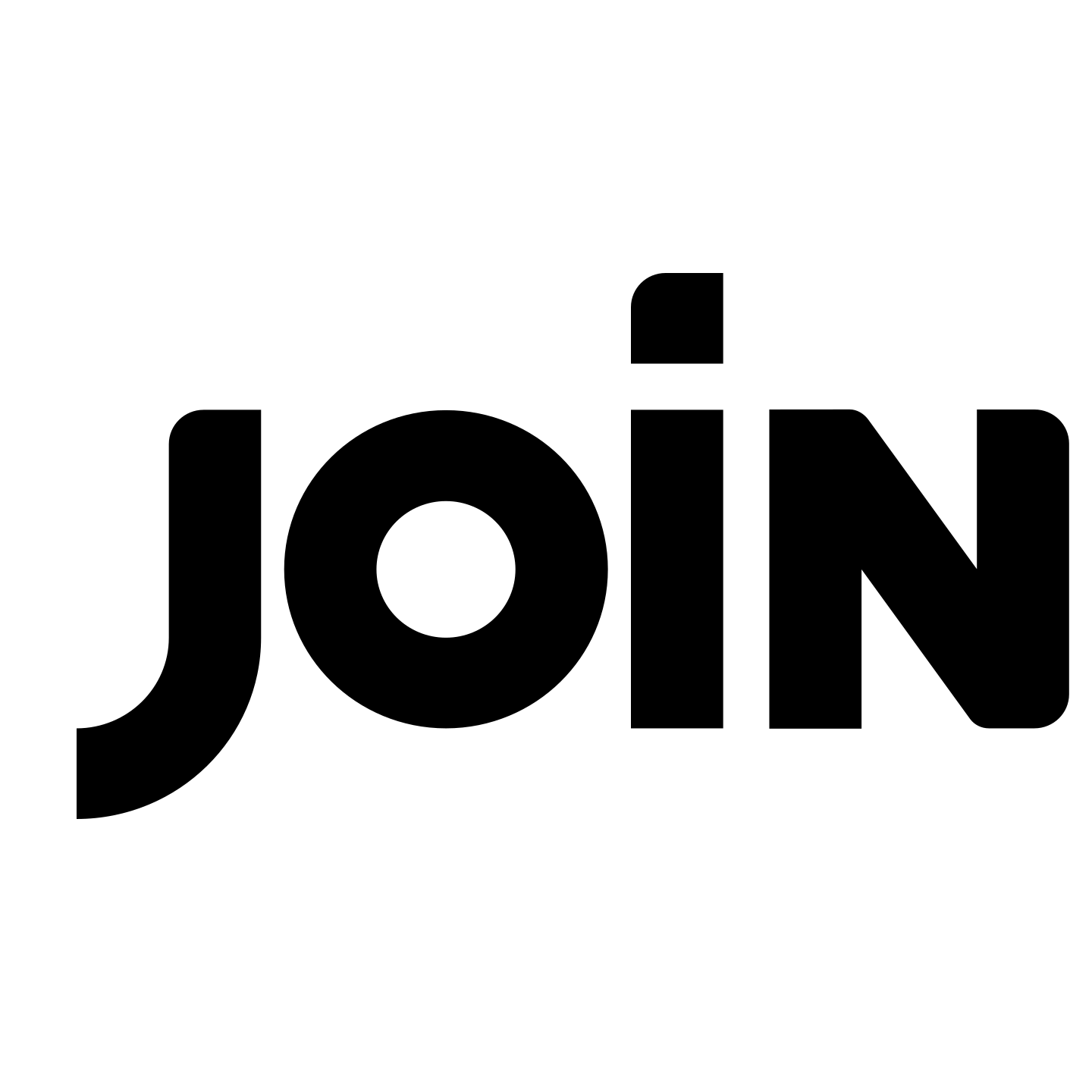大相撲部屋の米消費と価格高騰の影響:力士たちの食生活を探る
大相撲部屋における米の消費量と米価格高騰が力士たちの食生活に与える影響について詳しく解説します。

米価格高騰が相撲部屋に与える影響
大相撲部屋では、力士たちの食事が彼らのパフォーマンスに直結するため、米の消費量は非常に多い。例えば、高砂部屋では1日に15キロもの米を消費し、30キロの米袋は3日も持たないという。米価格の高騰は、こうした部屋の運営に直接的な影響を与えている。
各相撲部屋の対応策
- 九重部屋: 九重親方は、米がなくなった際の対策として、麺を増やしたり、炊き込みご飯やたけのこご飯を工夫していると語る。
- 木瀬部屋: 木瀬親方は、地方場所での差し入れが減少し、余剰分を施設に配ることができなくなったと明かした。
- 押尾川部屋: 押尾川親方は、地元の秋田米を購入し、麺を食べる日を設けるなど、バランスの取れた食事を心掛けている。
- 玉ノ井部屋: 玉ノ井親方は、福島からの米を大切にし、残ったご飯をチャーハンにするなど、ロスを避ける工夫をしている。
- 佐渡ケ嶽部屋: 佐渡ケ嶽親方は、山形の米を感謝しながら消費し、若い衆も米の価値を再認識していると話す。
米の価値と力士たちの意識
どの部屋も、米の価格高騰を受け、麺を増やしたり、食べ方を変えるなど、工夫を始めている。また、これまで以上に米の価値を認識しながら食事を楽しんでいる。力士たちにとって、食事はリラックスする時間でもあり、バランス良く、おいしく、楽しくいただくことが重要だ。
【佐々木一郎】